葬儀の主催者である喪主は、故人ともっとも縁の深い人がつとめます。通夜・葬儀の準備の最初に、遺族が協議して決めましょう。
重要事項
- 葬儀への希望はきちんと意思表示
- 故人ともっとも縁の深い親族がなる
- 複数が共同でつとめてもかまわない
- 親族がいない場合は友人・知人が代理でつとめる
喪主を決めるときは
葬儀の主催者である喪主は、故人ともっとも縁の深い人がつとめます。通夜・葬儀の準備の最初に、遺族が協議して決めましょう。
喪主とは葬儀の主催者
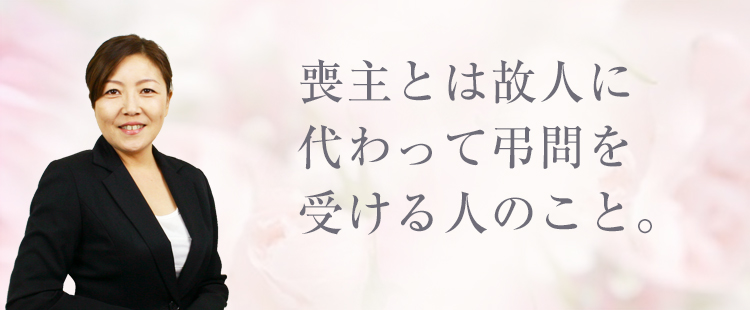
「喪主」とは、遺族の代表として葬儀を執り行い、故人に代わって弔問を受ける人のことです。通夜や葬式の準備をするにあたって、まず最初に決めましょう。喪主は葬儀を主催する立場なので、葬儀に関する希望はきちんと意思表示しておく必要があります。
喪主は故人と縁の深い親族
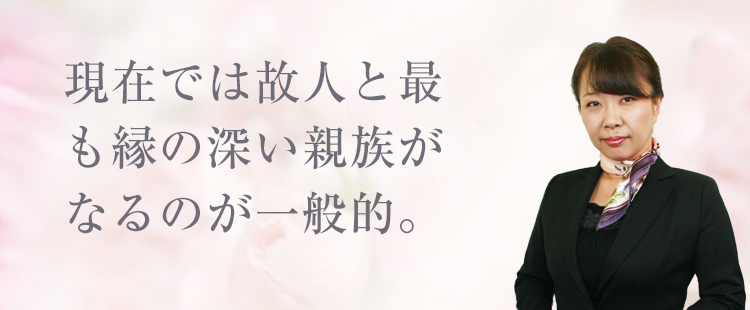
以前は法律上の相続人が喪主となりましたが、現在では故人ともっとも縁の深い親族がなるのが一般的です。故人が生前に自分の葬儀での喪主を指定していたときにはそれに従いますが、通常は故人の配偶者、子ども、親、兄弟姉妹の順になり、遺族が協議をして決めます。
他家に嫁いだ一人娘が喪主になることもできます。喪主はひとりとは限らず、何人かが共同でつとめることもあります。また、故人が血縁が薄く、喪主となる親族がいない場合には、友人・知人などが喪主の代理をつとめます。その場合は、「友人代表」「世話役代表」となり、喪主とは名乗りません。

親でも、子供の葬儀の喪主に
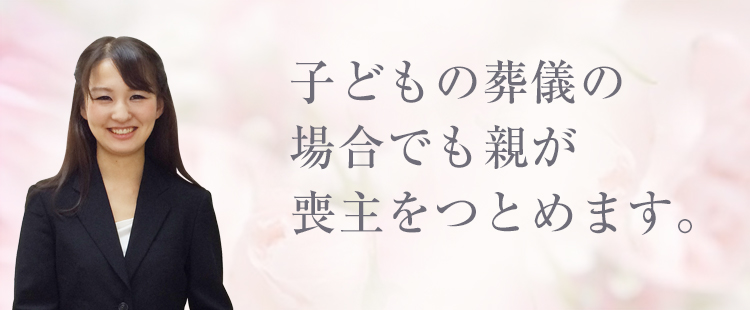
親より先に子どもが死ぬことを、「逆縁」といいます。昔は、親は子どもの葬儀にあたっては喪主にならないものとされ、火葬場にも同行しないことが多くありました。今ではこうした風習はうすれ、子どもにとって一番近い血縁である親が喪主をつとめるのが一般的です。
遺影は、暗い表情のものはさける
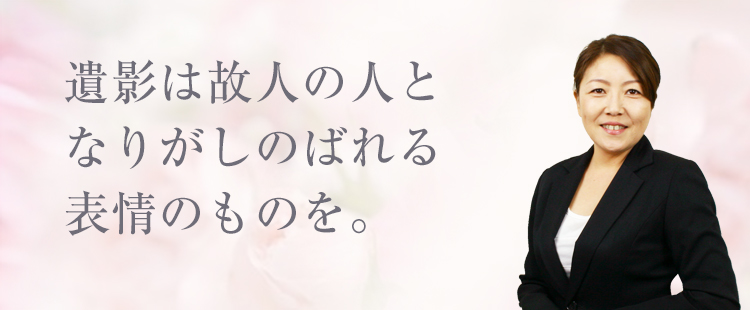
通夜・葬儀に、故人の遺影は欠かすことができません。四つ切り(上下296×左右240cm)のサイズに引き伸ばしたものがよく使われ、通常の額に入れた場合の料金は約2~3万円です。葬儀の形式によって額の種類もさまざまあり、また、額に花を飾ることもあります。
昔は白黒写真でしたが、今はカラー写真がほとんどで、周囲や背景も気になるものであればカットしてくれます。写真(紙焼き)やネガフィルムがあれば、葬儀社に手配を依頼します。アルバムから写真をさがすときは、療養中の暗い表情のものは避け、故人の人となりがしのばれる表情のものを選びましょう。
女性の場合、若いころの写真を望まれることがよくあります。遺影は葬儀のときばかりでなく、家にずっと飾っておくものですから、先々、若死にされたのではと誤解されないためにも、近影を用意しましょう。
喪主は誰が務める?
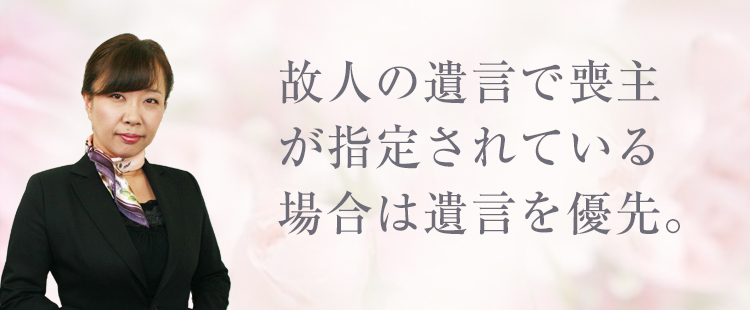
葬儀の準備を始めるにあたり、まず考えなくてはならないのは「誰が喪主を務めるか」ということです。現在では、故人の配偶者が喪主を務めるのが最も一般的な通例と言えるでしょう。故人の配偶者が病気や高齢であるなどの理由で喪主を務めるのが難しい場合であれば、血縁関係の深い方が喪主を務めるケースが多くなっています。具体的には
という順番で「血縁関係が深い」とされています。通常はこの慣例に従って親族で協議して決めることになりますが、故人の遺言で喪主が指定されている場合は遺言を優先します。故人に配偶者や血縁関係者がいない場合であれば、知人や友人、もしくは故人が利用していた介護施設などの代表者が喪主を務める場合もあります。
喪主と施主の違いは?
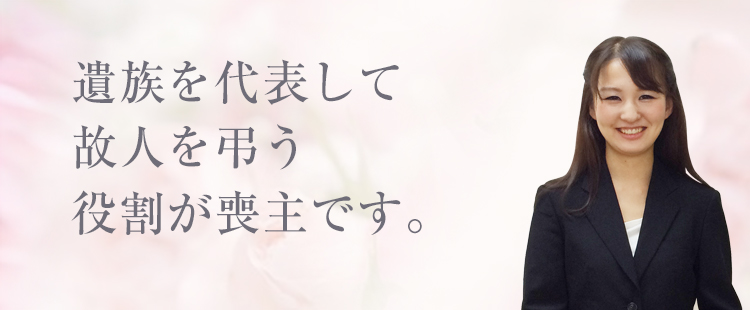
葬儀では「喪主」と「施主」という2つの似たような言葉を聞くことがあるかと思いますが、その違いについては意外と知られていないようです。まず、「喪主」の役割は遺族を代表して故人を弔う事です。
具体的には葬儀社との打ち合わせや参列者への対応、出棺の挨拶など、実務的な事の代表者と言えるでしょう。一方「施主」というのは主に葬儀の費用を負担し喪主をサポートする役割で、金銭的な面での代表者と言えます。
個人で行う葬儀では喪主が施主も兼任するケースが一般的ですので「施主」とう言葉は聞きなれない方も多いかもしれませんが、2つの言葉にはこのような違いがあります。喪主と施主が分かれている代表的な例としては「社葬」が挙げられます。社葬では故人の遺族が喪主を務め、葬儀の費用を負担する会社が施主を務めることになります。
喪主のあいさつについて
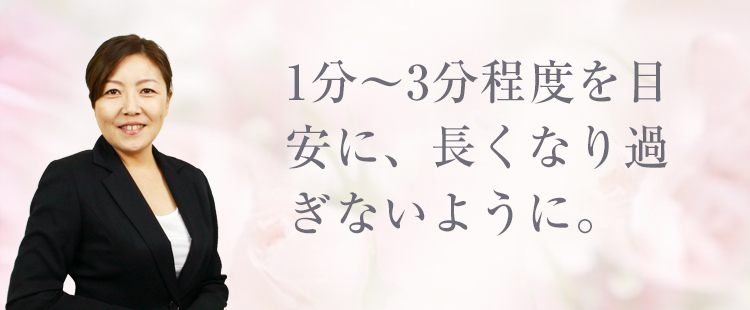
遺族代表として喪主が挨拶をするタイミングは複数回あります。まずはお通夜の読経の後、もしくは通夜振舞いが始まる前です。ここでは主にお悔やみに来ていただいた事へのお礼の言葉をお伝えします。
次は告別式の最中、もしくは出棺前です。ここでは故人を偲び、参列者への感謝の気持ちをお伝えします。また、四十九日の法要の精進落としの際にも喪主の挨拶が必要となるなど、葬儀だけではなく以後の年忌法要でも喪主の挨拶の役目は続いていきます。
通夜振舞いの習慣の有無など、葬儀の流れは地域によっても大きく異なりますので事前に葬儀社の方に確認しておいた方が確実でしょう。一般的な挨拶の内容は
となります。1分~3分程度を目安にして、長くなり過ぎないようにまとめましょう。縁起の悪い忌み言葉や重ね言葉は使用しないように気を付けてくださいね。

喪主も香典を出すもの?
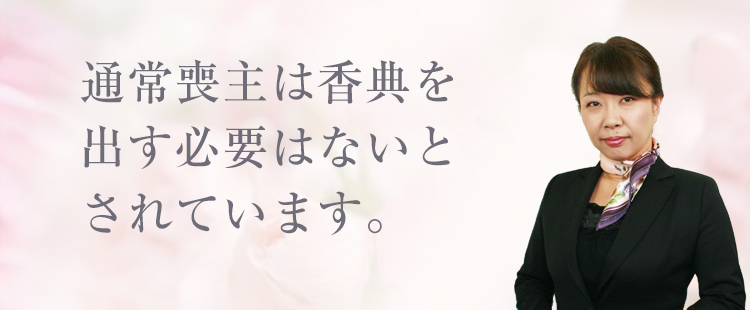
一般的に香典というものは、遺族の代表である喪主に宛てて参列者が持参してくるものです。従って、通常喪主は香典を出す必要はないとされています。また、香典は基本的に個人ではなく家単位で出すため、喪主の配偶者が香典を出す必要もありません。
ただし、あまりよくある事ではありませんが喪主が香典を出すケースもあります。それは、喪主とは別に葬儀の費用を負担している「施主」がいる場合です。一般的な個人葬では喪主が葬儀費用を負担している場合が多いのでこのようなことはありませんが、喪主と施主が別々の場合は喪主から施主に香典を渡すこともあります。
これは必ずそうしなくてはならないという訳ではありませんし、葬儀の費用を負担するのは施主であっても、会葬御礼品や香典返しを負担するのは遺族である喪主という場合も少なくありませんので、どのようなケースで喪主が香典を出すべきか一概に決めることは出来ないでしょう。気になる場合は施主や葬儀社に確認しておいた方がいいですね。
喪主の妻がやること
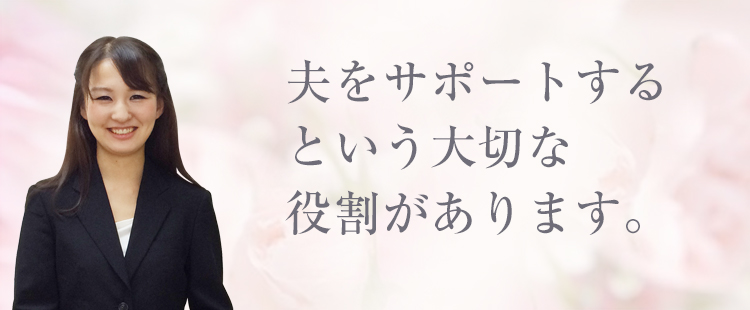
夫が喪主を務める場合、妻には夫をサポートするという大切な役割があります。喪主である夫を具体的にどこまでサポートするかは葬儀の大きさや地域によっても変わってきますが、参列者への挨拶やお茶出しなども喪主の妻の役割として挙げられるでしょう。
当日スムーズに進行できるように、あらかじめ夫とよく話し合っておくことが大切ですね。不安に感じる場合は経験者の方に相談してみるのもいいでしょう。
多くの参列者が見ている中で慣れない仕事をするのは簡単なことではありませんが、夫も喪主を務めるにあたって重圧や負担に感じている事が多いはずです。そういった心の負担を軽減してあげるのも、妻だからこそできる大事な役目ですね。
喪主の正しい服装
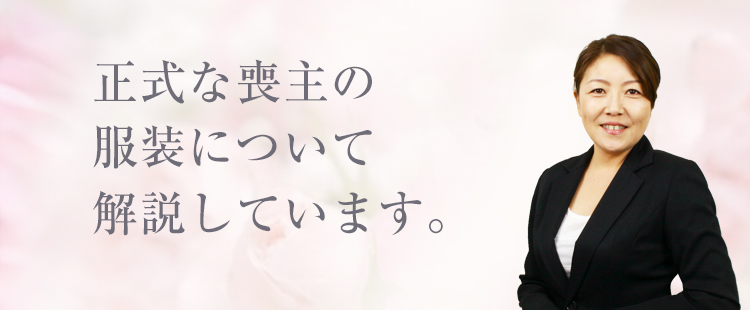
喪主が男性の場合、和服であれば黒羽二重の染め抜き五つ紋付に羽織袴。洋礼服の場合は黒のモーニングに黒のネクタイが正式礼装とされています。ただ、最近では喪主であってもブラックスーツに白のワイシャツという準礼服が主流となっています。ネクタイ、靴下、靴は黒のもので統一しますが、ネクタイピンは使用しません。靴やカバンなどは光沢のないものを選択しましょう。
喪主が女性の場合、和服であれば羽二重に染抜きの五つ紋付の黒の無地、白の足袋に黒の草履が正式です。帯揚げ、小物も黒で統一します。最近は女性でも洋服で喪主を務める方が増えてきており、洋装の場合は黒無地のワンピースやフォーマルスーツを着用します。
ボタンやバックルは共布(同じ布の生地)か、光沢のない同じ色のものを使用しましょう。靴は光沢のない黒色のパンプスが正式とされています。結婚指輪以外のアクセサリーを付ける場合は一連の真珠のネックレスを着用します。ピアスやイヤリングは可とされている場合もありますが、外しておいた方が無難ですね。
この記事に関係する商品
葬祭マナーカテゴリ