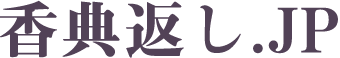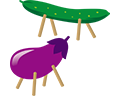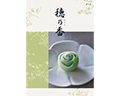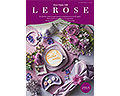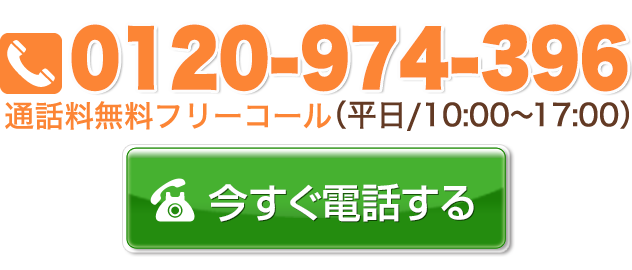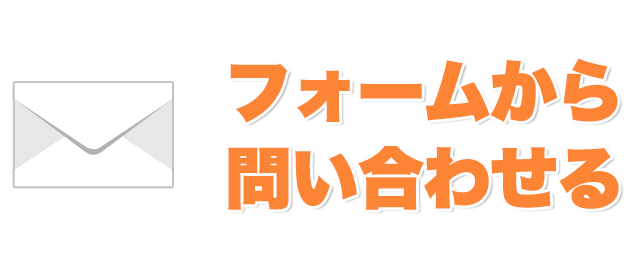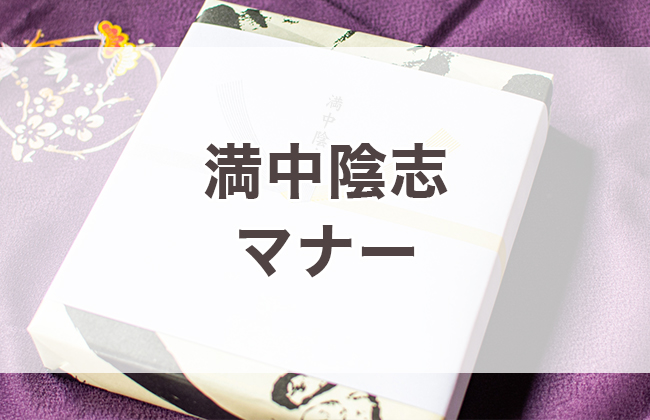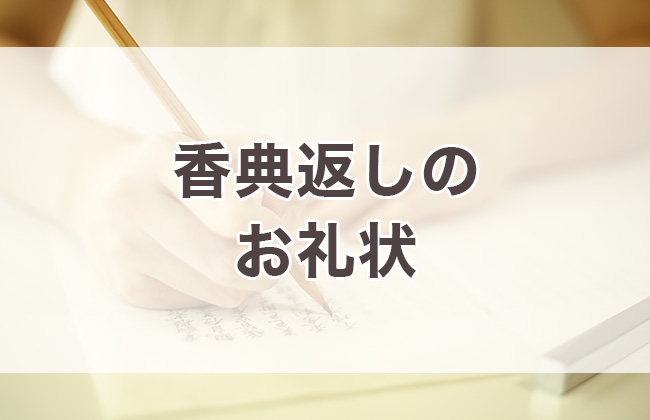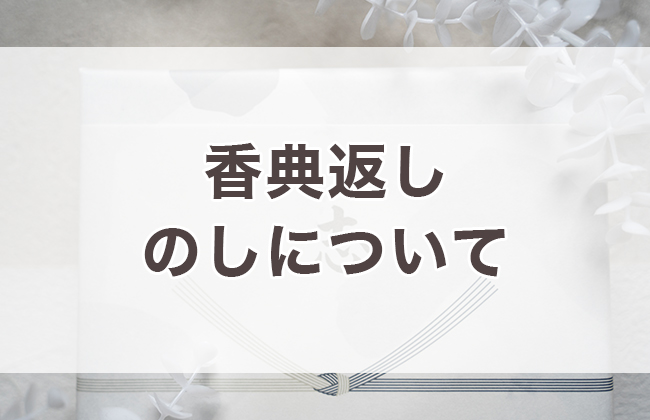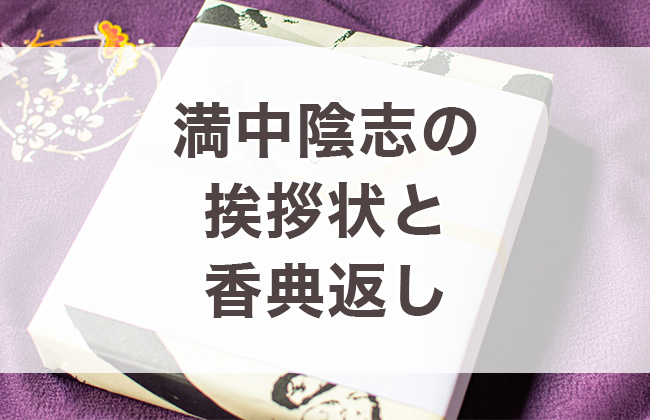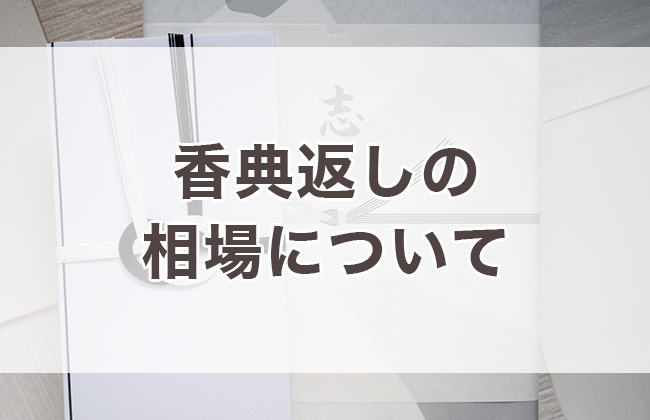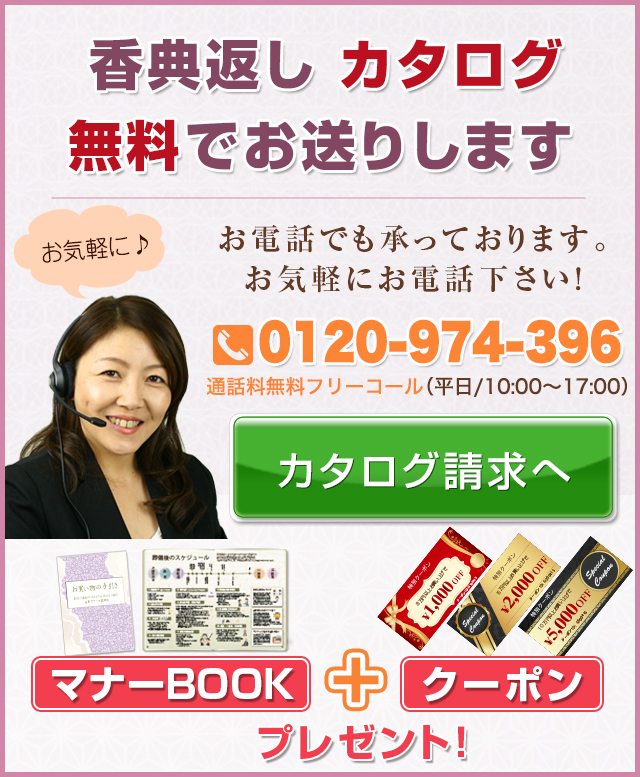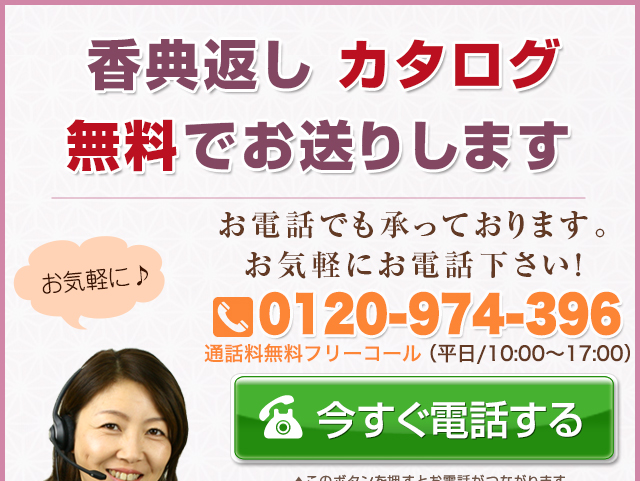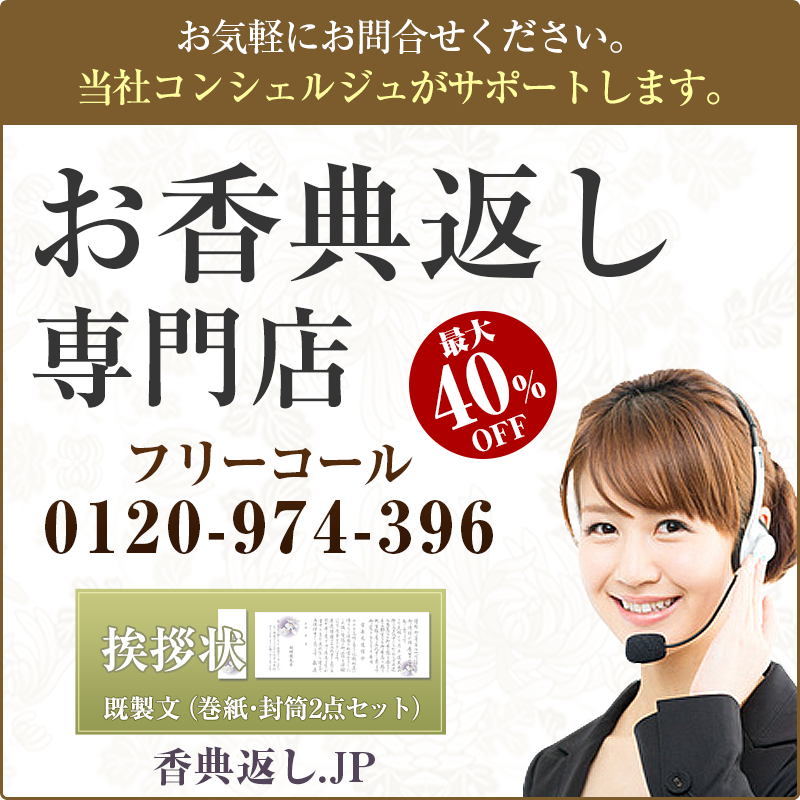お住まいの地域によっては普段は聞きなれない「粗供養」という言葉ですが、最低限の知識やマナーを知っておけばいざという時にも安心です。今回の記事で基本的な知識を身に着けておきましょう。
粗供養とは何?
粗供養とは?
粗供養(そくよう)とは、葬儀や法要の際に供養していただいたことに対して、感謝の意味を込めて粗品やお返しをお渡しすることです。お渡しする品物を「粗供養品」と呼びます。粗供養は主に関西や西日本で使われる言葉で、通夜、葬儀、法要などの返礼品のかけ紙(のし紙)の表書きに使用されます。
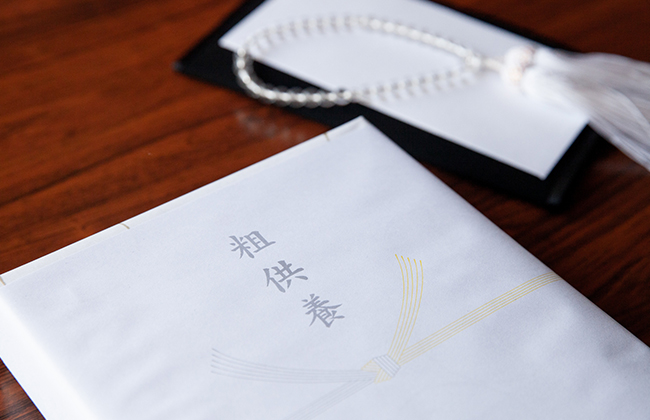
地域によっては「祖供養」と書く場合もあります。こちらは「ご先祖様への供養」という意味がありどちらも間違いではありませんが、通常は「粗供養」とするのが一般的です。東日本では表書きには「志」という言葉を用いる場合がほとんどですので、こちらの方が見覚えがあるという方も多いかもしれませんね。
会葬礼状に添えてお渡しする「会葬御礼品」として用意する場合、香典返しとして用意する場合、法要のお返しとして贈る場合がありますが、状況によって用意する品物の金額相場も変わってきます。
粗供養って誰がするもの?
葬儀や法要で供養していただいた方へのお礼の品である粗供養は施主(喪主)から贈るのが一般的です。デパートなどで確認しても、「粗供養は喪主にあたる人のみが用意するもの」と回答される場合が多いでしょう。
ただし、関西の一部の地域などでは法要の参列者が参列者の軒数分の品物を粗供養品として持ち寄る、兄弟など施主以外の親族も粗供養を用意して施主と同じように参列者に渡す、などのように、実際に「施主以外の人も粗供養を用意する習慣」があります。

仏事は地域によって驚くほどルールや風習が大きく違う場合がありますので、事前に地元の親族の方や葬儀屋さんに確認しておいた方がいいでしょう。
香典返しや満中陰志との違いは?
通夜や葬儀の参列者からお悔やみを頂いたら、感謝の気持ちにお返しするのが「香典返し」です。この香典返しは四十九日の忌明け後に贈るものとされていますが、最近では香典を頂いたその場でお渡しする「即返し」の風習も広まっています。
満中陰志とは「中陰が満ちる」、つまり忌が明ける事を意味する言葉で、主に西日本で四十九日法要後の忌明けの香典返しの品物を贈る際に表書きに使用されています。つまり、満中陰志は忌明けの香典返しと同じ意味という事になりますね。

これに対して「粗供養」は主に法要でいただいたお供えやご仏前のお返しとなり、香典返しや満中陰志とは意味合いが異なります。例えば、四十九日の法要当日に香典返しの品物を渡す場合は、法事の返礼品として「粗供養」を一品、葬儀や通夜でいただいた香典のお返し(満中陰志)の品物を一品用意することになります。
のし紙はつけるもの?
粗供養品にはのし紙(かけ紙)をかけてお渡しするのが正式なマナーとされています。のし紙には様々な種類がありますが、粗供養品には「白黒」もしくは「黄白」の結び切りの水引のものを選びましょう。
全国的には白黒の水引が主流ですが、関西や中国、四国地方の一部では黄白の水引が一般的になっています。弔辞は二度と繰り返したくない事ですので、一度結んだらほどけない結び切りの水引を使用します。
表書きに「志」と「粗供養」のどちらを書けばいいか、使い分けが難しいという方もいらっしゃるかと思いますが、どちらを使用しても問題ありません。ただ、粗供養と言う言葉は関西では一般的であっても全国的には知らない方もたくさんいらっしゃいます。関西、四国、中国地方以外では「志」とした方が無難かもしれません。
相場や平均金額を教えて!
粗供養品の金額相場はどのようなお返しの仕方をするかによっても異なってきます。葬儀当日にお渡しする会葬御礼品として用意する場合は500円~1,500円程度の場合がほとんどですが、香典返しとして用意する場合は頂いた香典の金額の半額~3分の1が基本とされています。

当日返しの場合は、頂く香典が5,000円~10,000円であると想定して、2,500円~3,000円相当の品物を用意するのが一般的と言えるでしょう。ただし、粗供養品の風習に関してはお住まいの地域によって大きく異なりますので、相場は目安として参考にする程度にとどめ、事前に周囲の方と相談してから金額を決めた方が良いでしょう。
人気の品物や好適品は?
粗供養品は不祝儀ですので、後に残らない「消えもの」を贈るのが良いとされています。粗供養品の定番は海苔や食品の詰め合わせ、個包装されたお菓子、お茶、コーヒー、洗剤、タオルなどの食品や消耗品です。持ち帰る方の事を考えて、軽くてかさばらないもの、置き場所に困らないものを選ぶように配慮することも大切ですね。

せっかくの贈り物ですので贈った相手に喜んでもらいたいのはもちろんですが、受け取る側の立場からすると後に残らずに日常で使用することが出来るシンプルなものの方が喜ばれる傾向にあります。
故人が亡くなって、葬儀の準備など慌ただしい中での品物選びは思いのほか心身に負担がかかるものです。遺族の負担にならないように、用意しやすく一般的に好まれている品物を選ぶという事も心がけておきましょう。
粗供養品の選び方
粗供養品を用意する際は、参列者への感謝の気持ちを込めて失礼のないように慎重に選ぶことが大切です。一般的に粗供養には「消えもの」、つまり形に残らない品物を選ぶのがマナーとされています。これらは実用性が高く受け取る方も気を遣わずに済むため、粗供養品として非常に人気があります。
一方で、粗供養品として避けた方がよいとされる品物も存在します。代表的なのは、肉や魚などの生ものです。これらは仏教の教えに反する「殺生」を連想させるため、不適切とされています。また、かつお節や昆布などの縁起物は祝い事に用いられるものとされ、弔事にはふさわしくありません。加えて、金券や商品券などは贈る側の金額が直接的に伝わってしまうため、受け取る方によっては不快に感じることもあります。たとえ便利であっても弔事の品としては避けた方が無難でしょう。
粗供養品を選ぶ際には、季節感を取り入れるのも一つの工夫です。たとえば、夏であれば涼を感じられる素麺や冷たい飲み物、冬であれば温かい飲み物やスープのセットなど、季節に合わせた品物を選ぶことでより気配りが伝わります。また、普段は自分で購入しないような少し高品質なタオルや洗剤といった日用品も人気があります。実用的でありながら特別感も演出できるため、贈る側・受け取る側の双方にとって満足度の高い選択といえるでしょう。

さらに、近年ではカタログギフトも粗供養品として注目を集めています。カタログギフトなら、受け取った方が自分の好みに合わせて商品を選ぶことができるため、好みが分からない相手にも贈りやすいというメリットがあります。価格帯も幅広く用意されているため、相場に応じて選びやすい点も魅力です。
故人を偲ぶ場である法要や葬儀の場にふさわしい贈り物を選ぶことは、遺族にとっても大切な心配りの一つです。形式だけにとらわれず、相手に配慮した品物を選ぶことが感謝の気持ちをきちんと伝えることにもつながります。地域の風習や相手との関係性を意識しながら、心を込めた粗供養品を用意したいですね。
粗供養に関するQ&A
粗供養を準備する際に、多くの方が悩む質問とその対応策についてまとめました。実際の場面で役立つ情報として参考にしてください。
Q.親族間で粗供養の品物や金額が異なる場合、どうすれば良いですか?
A.基本的には施主(喪主)の意向を尊重し、統一することが一般的ですが、特に故人と親しかった方などには個別に品物を準備する場合もあります。しかし、兄弟姉妹など近い親族がそれぞれ粗供養品を用意する場合は、事前に話し合って品物の種類や金額の範囲を決めておくと良いでしょう。大きな差が出ないよう配慮することが大切です。
Q.粗供養品を受け取らない方がいる場合は?
A.宗教上の理由や個人的な考えから粗供養品を辞退される方もいらっしゃいます。そのような場合は、無理に受け取っていただく必要はありません。「お心遣いは十分に伝わりました」とお伝えし、相手の意向を尊重しましょう。後日、感謝の気持ちを込めたお手紙を送るという方法もあります。なお、相手が粗供養品を辞退している場合には、手紙に品物を同封しないように注意してください。
Q.法要に参列できなかった方への粗供養はどうすべき?
A.香典やお供え物を送ってくださった方には、法要に参列された方と同様に粗供養品を贈るのが一般的です。郵送する場合は、丁寧な手紙を添えて、法要の様子や故人を偲ぶ言葉を添えると良いでしょう。送料や日持ちを考慮した品物を選ぶことも大切なポイントです。
Q.粗供養品の贈り忘れに気づいた場合は?
A.気づいたらすぐに対応するのが基本です。品物を用意して直接訪問するか郵送し、遅くなったことを丁寧に謝罪しましょう。「確認が行き届かず申し訳ありません」と伝え、感謝の気持ちを伝えることが大切です。できるだけ早く対応することが大切ですが、時間が経ちすぎている場合には、相手に気を遣わせないように配慮しましょう。

Q.外国人の参列者がいる場合の対応は?
A.外国人の参列者には、日本の粗供養の習慣について簡単な説明を添えると良いでしょう。英語や相手の母国語で短い説明文を添えたカードを用意しておくと親切です。また、宗教的な理由で受け取れない食品などがある可能性も考慮し、できれば事前に確認するか、無難な日用品を選択するとよいでしょう。海外では葬儀のお返しの習慣がない国も多いため、「日本の感謝を表す伝統的な習慣」として丁寧に説明すると理解が得やすくなります。
Q.複数の法要が重なった場合、粗供養品はどうすべき?
A.たとえば四十九日と一周忌が近い時期に行われる場合など、複数の法要が短期間に重なることがあります。その場合は、同じ方に同じような粗供養品を短期間で贈ることを避けるため、品物の種類を変えたり、一方をカタログギフトにするなど、受け取る方の好みや都合に合わせて選べるようにすると良いでしょう。また、「本来なら別々にお渡しするところ、まとめてのご挨拶となり申し訳ありません」といった一言を添えることで、失礼にならないよう配慮しましょう。重なった法要の意味を考え、少し特別感のある品物を選ぶという方法もあります。
Q.子どもがいる参列者への粗供養で気をつけることは?
A.子ども連れの参列者への配慮として、子どもも楽しめる粗供養品を検討するのも良いでしょう。例えば、大人向けのお菓子セットに子ども向けのお菓子を一つ加えたり、家族で楽しめるようなお茶やジュースのセットにするなどの工夫があります。また、子どもがいる家庭では荷物が多くなりがちなので、持ち運びやすさや、持ち帰りやすさにも配慮すると良いでしょう。法要の場に子どもを連れてくることに気を遣われている方も多いため、「お子さまと一緒に参列いただき、ありがとうございました」など、子どもの参列を歓迎する一言を添えると、親御さんも安心されるでしょう。
関連記事
葬祭マナーカテゴリ
- 香典返し
-
- カテゴリTOP
- 香典返しとは
- 香典返しと忌明けのあいさつ状
- 香典返しのマナーや作法について
- 香典返しの送る時期やマナーについて
- 香典返しを送る際のお礼状やマナー
- 香典のお礼と香典返しのお礼は立場が違います
- 香典返し挨拶状の文例などについて
- 満中陰志の挨拶状と香典返しについて
- 香典返しに添える手紙を書くときのポイント
- 香典返し「のし」について
- 香典返しの相場について
- 香典返しに商品券を選ぶメリット
- 香典返しを辞退する方法
- 高額な香典をいただいた時のお香典お返しマナー
- 香典返しの品物は何が良い?
- 香典返しでカタログギフトは失礼?
- 香典返し 親族(親戚)への対応の仕方
- 香典返し 会社や同僚へのお返しについて
- 香典返しの時期と金額相場
- 喪家・葬儀まで
- 弔問客
- 法要・供養
- 社葬