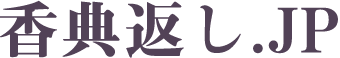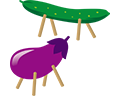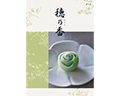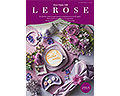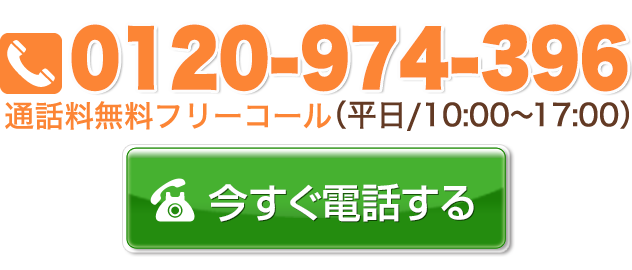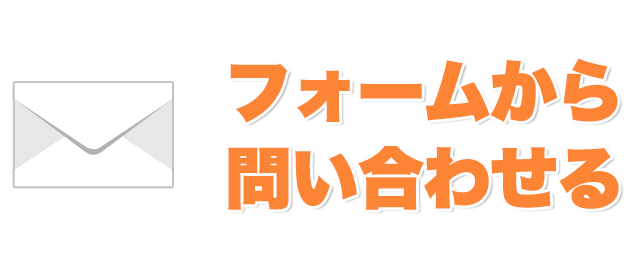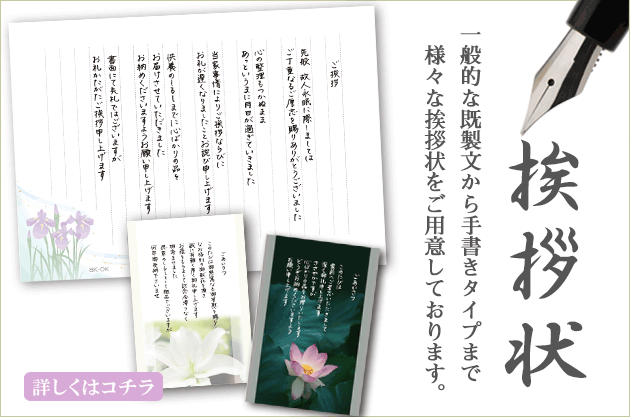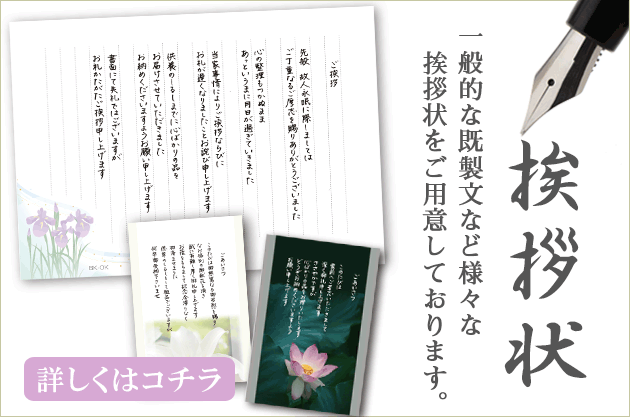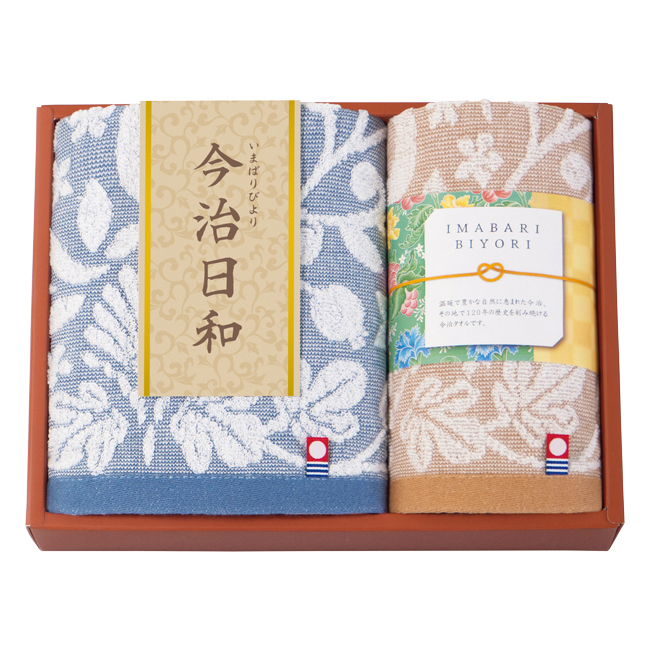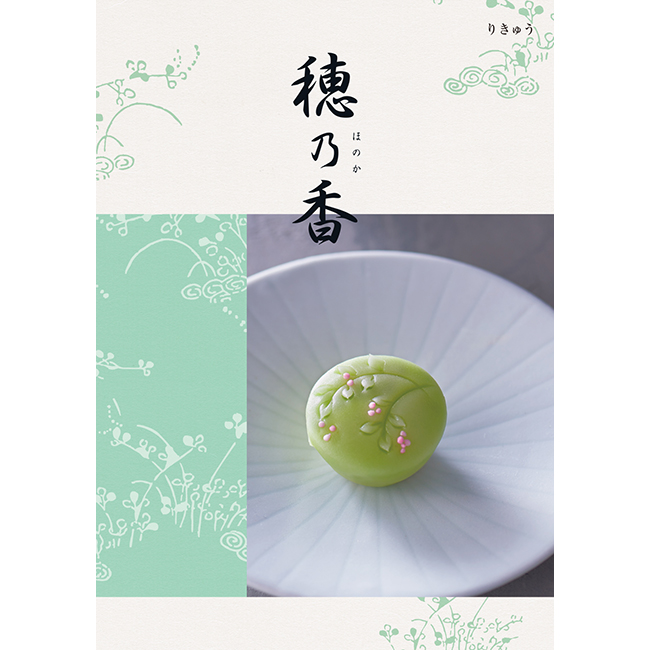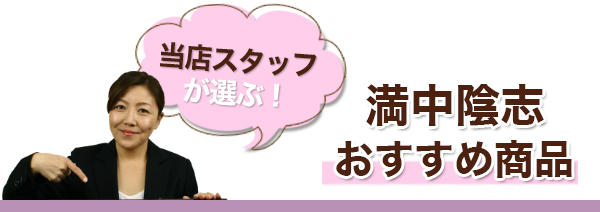「満中陰志」は主に関西地方を中心に使用されている言葉です。ご存知ではない方もいらっしゃるかもしれませんが、弔事に関する知識として覚えておいて損はありません。特に挨拶状や手紙、お礼状、添え状の書き方には押さえておきたいマナーがありますのでこの記事を参考になさってください。
満中陰志の挨拶状と香典返し
そもそも「満中陰志」とは?
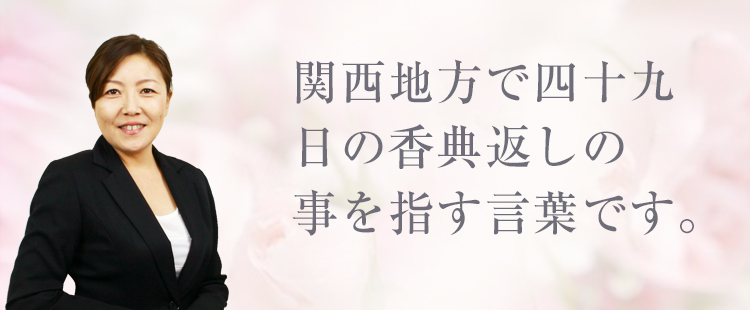
地域によっては「満中陰志」という言葉に馴染みがない方もいらっしゃるかと思いますが、これは「四十九日の香典返し」を指す言葉です。「中陰」というのは、亡くなられた方があの世へ渡っていく期間の事で、「中陰が満ちる」、つまり、四十九日の忌明けを迎える時に贈る「志」(感謝の気持ち)が「満中陰志」という訳です。
満中陰志は主に関西地方で使用されている言葉ですが、忌明けの香典返しと同義と考えて問題ありません。満中陰志には葬儀に参列し、お供えをしていただいた事に対する感謝の気持ちが込められています。
満中陰志は直接伺って、お礼の言葉と共に品物を手渡しするのが昔からの習慣でした。しかし、全国各地から参列することが当たり前の現代では直接伺うのが困難である場合が多いため、お礼の言葉を記載した挨拶状を添えて品物を郵送するのが一般的なマナーとされています。
挨拶状の基本的な内容は?
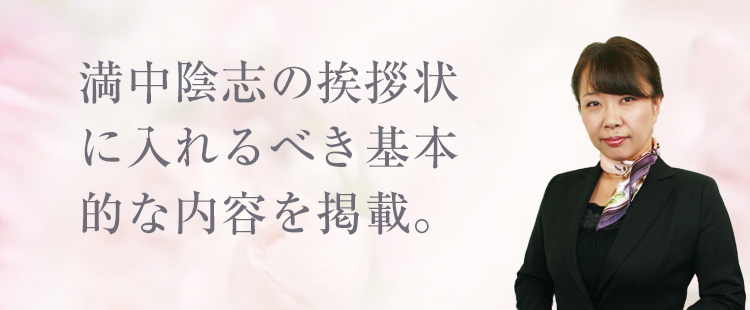
いざ満中陰志の挨拶状を書こうと思っても、一体どのように書いていいのか見当もつかないという方も多いのではないでしょうか。満中陰志の挨拶状に入れるべき基本的な内容と構成は以下のようになりますので、まずは参考にしてみるといいでしょう。
- 頭語(拝啓、謹啓など)
- 葬儀に参列し、香典を頂いたことに対するお礼
- 四十九日の法要が滞りなく済んだことの報告
- 満中陰志の品物を贈った旨
- 本来は直接ご挨拶に伺うべきところ、書面という略儀で済ませることへのお詫び
- 結語(敬具、敬白など)
- 法要日の日付
- 差出人の名前
頭語、結語は必ず入れなければならないものではありませんが、「両方入れる」「両方入れない」のどちらかにして下さい。2の葬儀に参列し香典を頂いたことに対するお礼に続いて、生前のお付き合いに対するお礼を述べても問題ありません。お礼状や挨拶状は簡潔に書くのがマナーとされていますので、あまり長々と書かないように気を付けましょう。

お礼状の例文
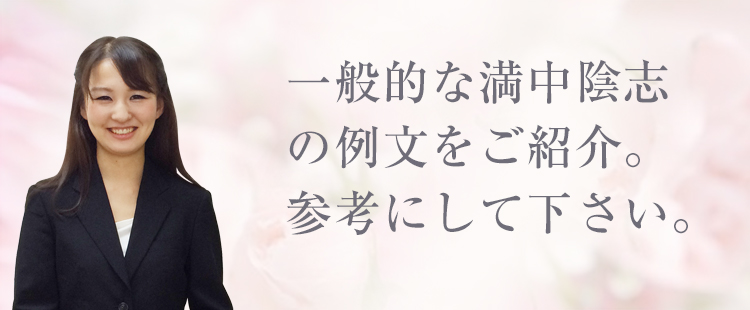
満中陰志のお礼状は普段使わない言葉や言い回しが数多く使用されていますので、このような挨拶状に関する知識を持たずに自作するのは簡単ではないかもしれません。以下に一般的な満中陰志の例文を紹介しますので、まずはこちらを参考にして作成してみて下さい。
謹啓 御尊家ご一同様にはますますご清祥の事とお喜び申し上げます
さて過日 亡父○○ 葬儀の節にはご繁忙中にもかかわらずご懇篤なるご弔慰をたまわり尚格別のご厚志に預かりご芳情の程誠に有難く厚く御礼申し上げます
お陰をもちまして満中陰の法要を滞りなく相済ませました
つきましては 供養のしるしとして心ばかりの品をお届けいたしましたので 何卒お納めいただければ幸いでございます
早速参上の上お礼申し上げるべき筈ではございますが略儀ながら本状をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます
謹白
お礼状は封筒?それともハガキ?
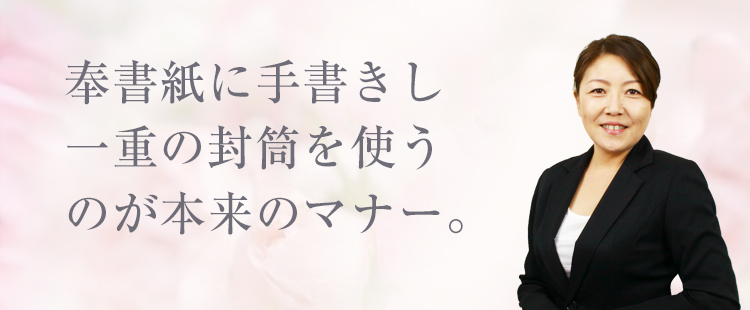
本来、満中陰志のお礼状は奉書紙1枚に手書きし、一重の封筒に入れて出すのが正式な形となっています。(二重封筒は不幸が重なるという意味となるため使用しません)しかし、最近ではハガキやハガキ大のカードに印刷する方が一般的になっていると言えるでしょう。
奉書紙を使用する場合でも文章は印刷というケースも少なくありません。葬儀屋さんに依頼したり、品物を購入したネットショップの無料サービスを利用して挨拶状を作成することが多いようですね。奉書紙やカードに印刷する場合は封筒に入れて、「挨拶状」と表書きをして送ります。
会社関係に送る場合は封筒に入れた方がより丁寧な印象になります。満中陰志の挨拶状は四十九日の忌明け後に出すため、薄墨ではなく濃墨を使用するのが通例です。これは手書きであっても印刷であっても同様ですので、間違えないように気を付けて下さいね。
お礼状を書く際の注意点
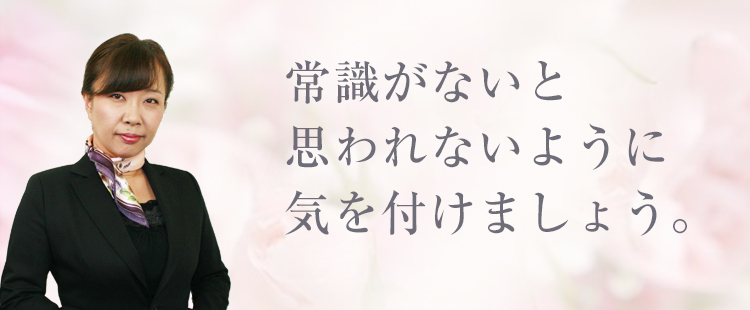
満中陰志のお礼状を作成するにあたって、いくつか注意点がありますのでご紹介します。
- 句読点は使用しない。
この理由には諸説ありますが、句読点には文章を止めるという意味があるため、法事が滞りなく進むようにという意味が込められているとも言われています。満中陰志以外でも挨拶状にはあまり句読点は使われませんので覚えておきましょう。 - 季節の挨拶は使用しない。
- 「ますます」「くれぐれ」などの繰り返す言葉は使用しない。
- 「逝去」は故人に対する敬語となるので身内には使用しない。身内には「死去」を使用する。
- 挨拶状を忌明けに贈る場合は濃墨を使用する。(地域によっては薄墨を使用する場合もあります。)
などが挙げられます。知らずに送ってしまうと相手に失礼になってしまいますし、常識がないと判断されてしまう事もあるかもしれません。しっかり押さえておきましょう。
宗教が変わると内容も変わる?
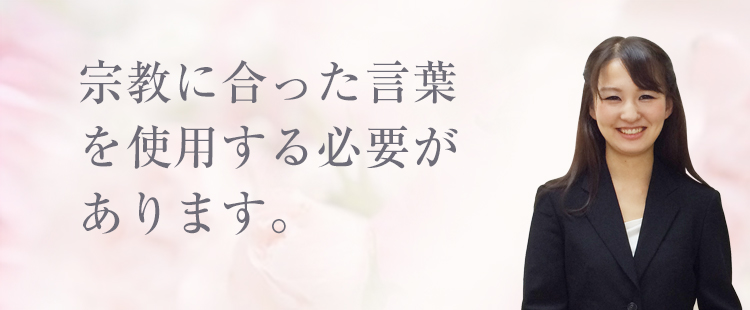
「満中陰志」や「香典」という言葉はそもそも仏教のものなのですが、日本では神道やキリスト教であっても葬儀に参列してお悔やみを頂いた事に対して、挨拶状を添えてお礼の品物を送る習慣があります。
宗教が変われば、挨拶状の中で使用する言葉もその宗教に合ったものを使用する必要がありますので注意が必要です。神道の場合、死去は「帰幽」、香典は「御玉串料」、香典のお返しを「偲草」と表現します。
また、神道では「五十日祭」が仏教の満中陰に当たります。キリスト教には「忌明け」という考えはありませんが、仏教の香典に当てはまる「お花代」や「御霊前」を頂いた場合は30日のミサや1か月目の召天記念日に「偲草」としてお返しをします。
お礼状を作成する場合、基本的な内容や構成は仏教のものを使用し、それぞれの宗教に対応する用語に入れ替えれば問題ありません。
この記事に関係する商品
葬祭マナーカテゴリ
- 香典返し
-
- カテゴリTOP
- 香典返しとは
- 香典返しと忌明けのあいさつ状
- 香典返しのマナーや作法について
- 香典返しの送る時期やマナーについて
- 香典返しを送る際のお礼状やマナー
- 香典のお礼と香典返しのお礼は立場が違います
- 香典返し挨拶状の文例などについて
- 満中陰志の挨拶状と香典返しについて
- 香典返しに添える手紙を書くときのポイント
- 香典返し「のし」について
- 香典返しの相場について
- 香典返しに商品券を選ぶメリット
- 香典返しを辞退する方法
- 高額な香典をいただいた時のお香典お返しマナー
- 香典返しの品物は何が良い?
- 香典返しでカタログギフトは失礼?
- 香典返し 親族(親戚)への対応の仕方
- 香典返し 会社や同僚へのお返しについて
- 香典返しの時期と金額相場
- 喪家・葬儀まで
- 弔問客
- 法要・供養
- 社葬